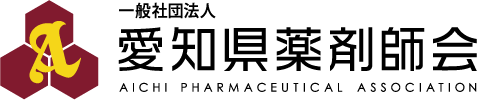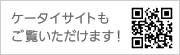13.吸入薬の正しい使い方
1.何のくすり?(効能・効果)
この薬は吸入用の気管支喘息治療薬と呼ばれるもので、大きく分けて3種類あります。
1:交感神経刺激剤・気管支をひろげて呼吸を楽にする吸入薬です。中程度発作(苦しくて横になれない歩行・会話困難)では有効ですが、重症発作時(呼吸困難のため歩行不能・会話困難)ではほとんど無効です。
2:抗コリン剤・気管支をひろげて喘息の発作を予防する吸入薬です。
3:副腎皮貫ホルモン剤・炎症を抑えて喘息発作を予防する吸入薬です。
また、吸入剤は、少量の薬を肺・気道に直接作用させるので、全身への影響も少なく内服薬に比べて安全な治療が期待できます。
2.正しい使い方
1.吸入口に異物がない事を確かめます。
2.容器をよく振ります。
3.容器を正しく持ち、吸入口を唇から指2本分(約4CM)離して構えます。
(小児の場合は、容器を口にくわえます。)
4.息を普通に吐き出します。
5.息を吸い始めると同時にひと押しし、口を大きく開け、5~6秒かけて、ゆっくり吸い込みます。
6.吸入剤を吸い込んだら、息を止めゆっくり10数えます。
(苦しければ無理をしないように)息を止めた後、ゆっくりと鼻から息を吐き出します。
7.吸入後、うがいができるときは必ずしましょう。うがいの水は飲み込まないように注意しましょう。(このうがいで、吸入剤による全身性副作用の、動悸・咽頭痛・口腔カンジダ症など、予防・軽減できます。)
*吸入補助器の効果
吸入補助器を使うと薬剤吸入による吐き気、咳込みなどを抑え、確実に薬剤を肺に到達させるので、より効果的な吸入が行えます。また、口腔への薬剤の付着を減らすこともできます。
大量投与を行っている患者さんでは、吸入補助器内に1度に複数回、薬剤を噴霧してまとめて吸入することで服薬しやすくなります。
また、吸入補助器の使用により薬剤の肺内分布が均一になり良いことが報告されています。 吸入補助器にはいろいろな種類があります。患者さんの呼吸機能によって適切なものを選びます。医師にご相談下さい。(製薬メーカーより入手可能)

3.生活上の注意
1.薬を自分勝手に止めたり、減らしたりしないこと。
2.禁煙を厳守しましょう。
3.腹式呼吸の練習を積極的に行いましょう。
4.喘息発作の原因になるホコリ・カビ・ダニの発生を防ぐため掃除をこまめに行い、室内・布団はきれいにしておきましょう。
5.猫や犬や小烏など、毛やふけが喘息の原因になりやすいので飼うのはひかえましょう。どうしても飼いたいときは、金魚などにしましょう。
6.食べ過ぎは発作の原因にもなりますので、食べ過ぎには注意し、バランスのよい食事をとりましょう。
7.痰を出しやすくするため水分を充分にとりましょう。
8.気温の変化に注意して、急な寒冷は避けましょう。
9.充分な睡眠・休養をとり、規則正しい日常生活を心がけましょう。
10.アスピリン等の鎮痛剤で発作が起きることがあるので薬は注意して服用しましょう。
11.ピークフロ一メーターを利用すれば喘息の状態が本当に良くなっているか、目で簡単に確認できます。ピークフロー値を毎日(起床時・就寝時)、測定し記録しましょう。<}>ピークフローメーターにはいろいろな種類がありますが、使い方はどれもほとんど同じです。

4.発作が起こったら
1.ゼーゼーが出始めたら早めに吸入剤を使う。
2.ゆっくり腹式呼吸を反復して行う。
3.運動が原因の時は安静にする。
4.発作が激しくなったときは、医師に指示されている臨時薬などを使用する。
5.発作が軽くならなければ、すみやかに医師の治療を受ける。
6.周囲の人に助けてもらえるよう、応急対応カードを常に携帯しておく。
(氏名・主治医・病院名・使用薬剤など記入)
Q&A
Q:いろいろな吸入剤を一度に処方されました、どういう順番がいいのでしようか。
A:1.気管支拡張薬 2.抗コリン剤 3.副腎皮質ホルモン剤 の順番で吸入して下さい。
気管支拡張薬は速攻性があり、気管支を拡張した後この順で吸入するとそれだけ多くの薬剤がすみまで行き渡るのです。次の吸入をするまで数分間、おいて下さい。(このうち2剤を併用する場合でも吸入順序は変わりません。)
Q:薬の残量が心配です。
A:噴霧回数カウンターを使用すれば、薬剤の残量を確実にチェックすることができます。
(製薬メーカーより入手可能)
*吸入剤の保管について
- 日光の当たるところ、火気の近くにはおかないで下さい。
- 室温(1℃~30℃)で保存しましょう。(冷蔵庫には入れないで下さい)
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 地方自治体により定められたポンペ廃棄処理方法にしたがって捨てましょう。
- ポンペに穴をあける場合は空にしてからあけて下さい。・ポンペは火中に投入しないで下さい。